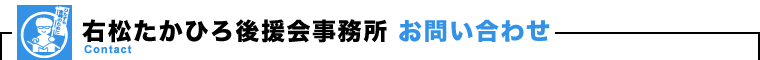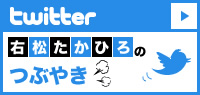ホーム > 活動ブログ
視察・調査活動
成長産業・TPP対策特別委員会・県外調査(1日目)
2013年11月05日
本日から2泊3日で、成長産業・TPP対策特別委員会の県外調査が行われます。初日の今日は、朝9:50の飛行機で、羽田経由で青森に向かいました。羽田空港の滑走路が1本閉鎖された関係で、青森空港に到着したのは、予定より1時間以上遅れ、15:30でありました。その後すぐに移動し、青森県庁に16時過ぎに到着し、行政調査を行いました。

青森県庁での調査目的は2つで、一つは「青森県の食産業振興に関する取り組みについて」、もう一つは「青森県エネルギー産業振興計画について」でありました。
「あおもり食産業の振興に向けて」については、青森では知事の意向でいち早く、平成20年度から「攻めの農林水産業」を掲げ、PB(プライベートブランド)づくりならびに食品加工業者を育てることを眼目に取り組まれています。具体的には、食産業づくり推進体制の確立に向け、あおもり食産業連携アドバイザーとの契約や“食産業連携企画会議”を毎月実施しているとのことでした。さらには、ABC(アグリ・ビジネス・チャレンジ)相談会として、県内6カ所、12か月で72回もの開催もしています。そして、事業者向け「食」サイトの開設や食品製造業者の情報などを構築し、マッチングなどを積極的に行っていることでありました。本県にとっても、さまざま参考になる取り組みを伺った次第です。
右松たかひろ
成長産業・TPP対策特別委員会・県南調査(2日目)
2013年08月28日
成長産業・TPP対策特別委員会の県南調査2日目となりました。まずは、都城の「イシハラフーズ株式会社」を訪問しました。石原社長自らパワーポイントで、食品加工業の最先端を走ってきた実績を基に、まさに現場サイドから見たフードビジネスにおける本質を鋭く問題提起されました。
「ビジネスモデルの流れが、今、大きく変わってきている。」、「逆6次化の発想で、加工会社が原料を確保するために農業分野に参入していった。」、「機械化、ライン化をいかに進めるか、常に進化させていった。」・・・説得力のある提言をいくつもいただき、また行政の役割についても、自らの考えを述べておられました。大変参考になる現地調査となりました。

続いて、午前中2軒目になりますが、高崎町の「株式会社 ミヤチク」を訪問しました。売上高が418億9,200万円(口蹄疫前が450億円)で、工場での牛・豚の処理頭数の推移、部分肉製造の推移、営業実績の推移、さらには輸出の推移の過去7年の比較表から、様々な意見交換を行いました。また、地域別売上構成の表からも強い地域と弱い地域が表れていることからも、今後どの地域に力を入れていくべきか、さらには、2期連続和牛能力共進会最優秀賞(日本一)の実績をいかに販路開拓に生かしていくか等々についても、忌憚なく意見を交わすことが出来ました。意見交換の後は、工場内も視察しました(下写真)。



今回の成長産業・TPP対策特別委員会での調査行程の最後の訪問地は、「株式会社ローソンファーム宮崎」でありました。宮崎の中邨社長と本部の戦略室から担当者が来られ、取り組みの内容や方向性について詳しく説明をいただきました。さすがに大手企業だけあって、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100の各店舗形態におけるターゲット戦略がしっかりしていること、そして、宮崎での農業参入の意図ならびにクラウドシステムを取り入れた管理体制の強化など、会社の明確な経営方針が理解できた次第です。

今回も大変有意義な調査活動となりました。
右松たかひろ
成長産業・TPP対策特別委員会・県南調査(1日目)
2013年08月27日
今日から1泊2日の行程で、成長産業・TPP対策特別委員会の県南調査が行われます。朝9時15分に県庁を出発して、まず綾町に向かい、岩下地区の小水力発電設備について、概要説明・意見交換を役場で行ったのち、現地調査も行いました。
下の写真でも分かるように、有効落差はわずか0.78メートルで、最大出力は1.5KWになります。年間発電電力量は、約4,800kwhで、売電価格が35.7円/kwで算出すると、年間171,360円で一般家庭の1件分程度です。ちなみに、県単事業の小水力発電等農村地域導入支援事業を使い、事業費が1,000万円で、内、県費を550万円支出しています。このことからも、とても採算に合うものではなく、用水路を活用した再生可能エネルギーの話題づくりで、地域活性化を図ることを目的とした事業と言ってよいと思います。
下写真1枚目がクロスフロー型水車の発電機で300万円程、2枚目が配電盤で500万円程との説明がありました。また、同じ水路を使い、3~4基の発電機増設も可能で検討中とのことでありました。


続いて、一路、鹿児島県庁に向かいました。鹿児島県のフードビジネスにおける取り組みを調査する目的になります。執行部の説明の中で印象に残ったのは、「大隅加工技術拠点施設(仮称)」についてでありました。高付加価値型農業の展開を目指して、来年平成26年度に完成予定の施設です。①加工ライン実験施設、②加工開発実験施設、③流通技術実証施設、④企画・支援施設、の4つの機能があり、鹿児島県の食品加工における歴史の深みと、さらなる上を目指す取り組みに、並々ならぬ熱意を強く感じた次第です。本県も、フードビジネスを成長産業に位置付けているので、今後の展開を戦略的に全力で取り組まなければなりません。

調査を終え鹿児島県庁舎を出ると、ちょうど桜島が噴煙を上げていました(下写真)。つい先日の8月18日に観測史上最高の噴煙でドカ灰を降らせたばかりですが、鹿児島県民にとってはこの風景は日常的なものなのだと感じた次第です。

夕方5時前に調査を終え、宿泊地の都城市へ戻りました。
右松たかひろ
厚生常任委員会・県外調査(3日目)
2013年08月22日
厚生常任委員会・県外調査の最終日は、滋賀県庁を訪問しました。調査目的は滋賀県の「医師確保対策」についてになります。

滋賀県内の医師の状況について数値報告があり、H25現在で、初期研修医を除く病院統計で、常勤が1,625人で、内、女性の割合が17%、非常勤で1,883人で、内、女性の割合が21%と女性医師の割合が大変高くなっています。その背景には、例えば滋賀医大の40%は女学生で、これは全国トップクラスになりますし、制度面でも女性医師の働きやすい環境づくりとして、女性医師職場復帰研修支援事業(20万円×6ヶ月×1人)や女性医師臨床復帰奨励事業(20万円/月×12か月×1/2×1人)、女性医師離職防止事業(200万円/病院×1/2×3病院)、さらには、子育て医師のためのベビーシッター費用補助など手厚い支援策で県行政がバックアップしているところからも数値で出ています。
なお、本県でも取り組んでいますが、平成21年に滋賀大学に寄付講座を設けて医師確保につなげていったことや家庭医療センターで家庭医・総合医を養成していくことなど、取り組み状況を執行部から説明をいただいた次第です。
今回の県外調査活動では現地調査はもちろんのこと、多くの資料もいただきましたので、宮崎に戻り次第、チェックをしていきたいと思います。大変充実した2泊3日の厚生常任委員会・県外調査となりました。
滋賀県庁での1時間30分の調査活動を終え、伊丹空港へ向かい午後2時の便で宮崎に戻り、県外調査の全行程を終えました。
右松たかひろ
厚生常任委員会・県外調査(2日目)
2013年08月21日
厚生常任委員会県外調査2日目は朝8:15に宿泊先を出発し、「兵庫県災害医療センター」に伺いました。兵庫県災害医療センターは、平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を受け、その教訓と経験に基づき復興への思いを実践するために平成15年6月に開設され、同年7月に基幹災害拠点病院に指定されています。

正面真ん中の3人で、右から兵庫県災害医療センターの中山センター長、川瀬副センター長、村本看護部長を始め、6名の医師・職員の方々に対応いただきました。本県がドクターヘリを導入した際に、ここ兵庫県災害医療センターで事前研修をされたとのことでした。大きな調査目的の一つは、「ドクターカー」になります。すでに10年前から先駆的取り組まれています。稼働状況も、センター開設の年の平成15年9月から運行を開始しており、16年の797回を最大に、昨年までに4,420回稼働しています。365日24時間、運行しており、とりわけドクターヘリが運行できない夜間の救命救急を大きく担う存在になっています。稼働回数の実に3分の2が、夜間や週末になっているとのことでした。実際に出動要請があれば、救急部専属医師が1名、看護師1名、救命救急士2名、専属運転士1名の計5名が一つのクルーとして現場に駆けつけることになりますので、ドクターカーを365日24時間運行するにおいては、人材の確保と配置は重要な要件となってきます。

災害や救急事態発生の際に、情報の一元管理や関係機関に連絡調整するという重要な「情報指令センター」も視察をさせていただきました。実際に、6日前に発生した福知山花火大会の露店爆発事故でドクターカーを出動させた当日の緊迫した状況を時系列で説明してくださいました。

続いて、東大阪市の「ハイワークひびき」(就労継続支援B型事業)を訪問しました。ここは、民間会社である鉄工所の4階に作業所があり、全国でも珍しい設置形態になっています。定員は20名で、その半数以上が重度の障がい者の方々です。作っているものは本格的な焼き菓子で、私たちもマドレーヌを試食させてもらいましたが、見事な美味しさでした。多くの購買者がいるのがよく分かりました。さらに素晴らしいのは、障がい者の作業工賃の向上に強く取り組まれており、大阪府平均の就労継続B型17,000円を大きく超える25,000~50,000円の給料を支給されているところです。収益をしっかり保ち、障がい者の方々が、働くことに誇りを持ち、生活の向上に取り組まれている授産施設でありました。


2日目最後に訪問したところが「滋賀県自殺予防情報センター」になります。精神科医療機関も敷設されてある滋賀県立精神保健福祉センター内に設置されており、自殺対策の専門拠点となっています。GK(ゲートキーパー)養成から、自殺に至る要因、まわりにいる人の対処の仕方など本質的な自殺対策の現場に至るところまで、下の写真2枚目真ん中の精神科医で精神保健福祉センターの辻本所長を中心に、担当の方々と有意義な意見交換をさせていただいた次第です。


右松たかひろ
厚生常任委員会・県外調査(1日目)
2013年08月20日
今日から厚生常任委員会の県外調査が行われます。朝9:50の飛行機で伊丹空港に向かい、到着後、京都に向かいました。
訪問先は「京都府家庭支援総合センター」になります。ここは、児童虐待やDV、ひきこもり対策の取り組みを先進的に行っている機関になります。2時間半にわたり、意見交換と館内視察をみっちり行わせていただきました。




まず特筆すべきは3年前の平成22年4月に京都児童相談所、婦人相談所、身体障がい者更生相談所、知的障がい者更生相談所の4つを統合し「京都府家庭支援総合センター」を発足したことにより、家庭を取り巻く、複雑・多様化する様々な相談をワンストップで応じることが出来ている点になります。統合のメリットとして具体的には、①一つの家庭で複合的に起きているケースが多い、児童虐待、非行、DVなどへのトータルな支援が可能になったこと、②18歳以上、未満で担当が分かれることなく、同一機関で生涯にわたる一貫した継続的支援が可能になったこと、③専門職員の集中配置により、専門性が向上し、質の高い相談体制が敷けるようになったこと、④府の福祉の中核機関として、市町村等との連携が非常に強化されたこと、を挙げられました。これは、大変参考にすべき取り組み事例と考えた次第です。
私からは、3点質疑をさせていただきました。一つは「そもそも統合するきっかけになったのは、直接的な事案があったのか、あるいは担当部署の高い問題意識があったのか」、統合のきっかけを伺いました。また、二つ目として「経路別受理状況から、近隣知人からの通告が2年で倍に増えた要因について」伺いました。そして3点目として「南部地域が受理件数が4年で倍に増えている要因や地域の特性について」伺いました。~これについては、本年4月に南部家庭支援センター所管において「宇治児童相談所京田辺支所」を開設し、迅速に対策を講じておられます。以上の3点の質疑とも的確な回答を頂き、今後の宮崎県政にも、十分に生かしてまいりたいと感じた次第です。大変有意義な調査活動になりました。
右松たかひろ
成長産業・TPP対策特別委員会・県北調査(2日目)
2013年07月11日
成長産業・TPP対策特別委員会の県北調査2日目になります。延岡を出発して川南町へ向かいました。訪問先は「みやざきバイオマスリサイクル株式会社」。ここは鶏ふんを燃料とした発電施設では日本一の規模で、その先進的な取り組みを視察するために、全国から毎年多くの人が見学に訪れる発電所です。


施設見学に先立ち、多くの意見交換をしました。平成16年に家畜排せつ物の適正処理を促す法律が施行されるともに、平成17年からバイオマス発電所の営業が開始されます。年間13万2千トンもの鶏ふんを焼却する能力があり、暦日稼働率90%でほぼ最大限の稼働がなされています。当初は売電単価が4円だったものが、事業スタート時に8円、そして国の再生可能エネルギーの全量買い取り制度で平成24年9月から17円になり、収益が上げれるようになり、22年度決算では1億8千万の利益、法人税を差し引いて、1億1千万の純利益を出すまでになっています。出資者(株主)構成や鶏ふん調達から発電までの事業スキームはよく考えられた内容で、鶏ふんのにおいを出さずクリーンな発電システムとも、一見に値する、まさに本県が誇るバイオマス発電所と感じた次第です。


川南町をあとにして国富町に向かいました。調査先は、国富第1メガソーラーと第2メガソーラーになります。ここは、矢野産業株式会社が所有する土地7ヘクタールに、合計で3.3メガワットのメガソーラーを、ソーラーフロンティア株式会社との共同で設置をし、今年の3月から稼働しています。最大の特徴は、通常のシリコン系よりも実発電量が多いという研究結果が出ている「CIS薄膜太陽電池」を利用しているところです。その特徴等も意見交換で伺ったところです。また、矢野産業が開発した砕石商品である「美砂(ミサゴ)」を敷いて、雑草の生息を予防し、メンテナンスにおいても工夫がされていました。

2日間の最後の訪問調査先が、九州電力宮崎支社になります。田處支社長を始め執行役員の方々と、再生可能エネルギー関連の申し込み状況から川内原発、電力の自由化に関することまで幅広い内容で、とても有意義な意見交換をさせていただきました。意見交換のあとは、発電管制室まで見学をさせていただき、大変ありがたく思っております。

右松たかひろ
成長産業・TPP対策特別委員会・県北調査(1日目)
2013年07月10日
今日から1泊2日の日程で、成長産業・TPP対策特別委員会の県北調査が行われます。
初日の今日は、まず、宮崎県食品産業協会との意見交換を行いました。食品産業会社の経営者で構成される協会役員、および中小企業団体中央会に所属する事務局の人たちとの意見交換は大変有意義なものでした。私からも、県内食品産業の現状と共通課題の中からパッケージデザインの見直し・改良について、また食品産業全体の底上げ策について、ならびに協会役員からご意見のあった認証制度について、意見を交わさせていただきました。

続いて、川南町の有限会社 協同ファームに伺いました。加工工場などを視察したあと、役場にて、日高社長との意見交換を行いました。同社の「まるみ豚」は第8回宮崎県肉畜共進会でグランドチャンピオンを受賞しており、最高の素材です。それを支えているのが、「豚への愛」と「伝説的な井戸から引く水」と「自家配合のエサ」。まだ若い、日高社長の強い情熱が十分に伝わる意見交換となりました。川南を盛り上げようとする地域貢献にも注力されており、ぜひ、大きく成功してもらいたいと思いました。


初日の最後は、延岡市の千徳酒造株式会社を訪問しました。県内39社ある酒造会社で、清酒のみの製造は今や千徳酒造のみになります。20年前は清酒の酒造会社は18社あったそうです。長年営むことが出来ているのは地元延岡に支えられてのことと力説されていました。新商品の開発も怠らず、積極的に商品展開されており、宮崎市から依頼され製造した「発泡清酒 はじまり」は記紀編さん1300年を記念して、江田神社近くの水田で、「みそぎ池」の水を注いで育てた酒米を使用しています。女性に好評を博しそうなフルーティで美味でした。

右松たかひろ
厚生常任委員会・県南調査(2日目)
2013年07月03日
厚生常任委員会・県南調査の3日目は、まず小林市の「こすもす保育園」を訪問しました。佐野園長との意見交換で「小林市内も保育士不足で5~6年前は職員募集をかけたらすぐに来ていたが、今はなかなか集まらない」とのことでいた。保育園は、あんしん子ども基金を活用して先々月の5月26日に新園舎の落成式を行ったばかりで、様々な工夫を凝らしたきれいな園舎で、子ども達もみんないきいきと元気に過ごしていました。ここの特徴は、「病後児保育」をしているところで、病気を患い回復期にある乳幼児(0歳~小学3年生まで)を選任の看護師と保育士でお世話をされています。共働きなど保護者が働いて、仕事が休めない世帯では大変助かっているとのことでした。

園児たちはあいさつも良く出来ていて、きれいな園内を元気に動き回ってました。

そして、今回の県南調査の最後の訪問先が「宮崎歯科福祉センター」になります。平成14年11月から開業されて、10年経過しましたが、毎年事業を拡大されているとのことでした。障がい者の歯科医療は大変難しく、一般の歯科医院では受診が困難で、このような専門の歯科は非常に重宝されていて、平成24年度の患者数は7,721人で、全国で3位とのことでした。他県からも、視察などで訪問してくる機会も多いようです。県内には障がい者の方は7万人おられます。まだまだ潜在ニーズが多いことを考えると、歯科医が言われていた「宮崎市から遠いところでも治療が出来るように、第2歯科診療所が県北にあれば・・・」との思いがよく分かる次第です。

以上で、今回の2泊3日の厚生常任委員会・県南調査のすべての行程が終了しました。今回も大変充実した委員会の調査活動となりました。
右松たかひろ
厚生常任委員会・県南調査(2日目)
2013年07月02日
厚生常任委員会・県南調査の2日目は、県民・団体との意見交換ということで、福祉べいすんネットワークの方々との意見交換会から始まりました。障がい者が地域でいきいきと日常生活や社会生活を営むことが出来るようにと、各福祉サービス事業者が連携して、平成20年4月に発足したのが「福祉べいすんネットワーク」です。(べいすんとは英語で「盆地」をあらわすとのこと~都城盆地から)。 ネットワーク作ることの大変さや就労支援で苦労されていることなど詳しくお聞きすることができ、予定時間がオーバーしてしまうほど大変充実した意見交換会となりました。


続いて、県立みやざき学園を訪問しました。この施設は、児童相談所長の措置や家庭裁判所の審判により、現在、中学生の男子8名、女子4名の計12名を受け入れています。入園者の8割が家庭でのネグレクトの経験を持っているとのことでした。ここでも、初日の訪問先の様に、寮の中で出来るだけ家庭生活を味わってもらうような工夫がなされています。なお、概ね1年程度の入園期間で、育て直しを行っているとのことでした。


2日目最後は、小林のこばやしハートムが運営する茶飲ん場「ゆきやま商店」を訪問しました。代表の尾崎さんが平成19年7月に高原町で開催された「自殺対策フォーラム」に出席した際、自殺者が多いことに驚き、高原町と小林市の有志20名が集まり、「自殺しそうな人に直接声をかけて思い留まらせてはどうか」という意見が出て、「1日30人と話そう会」を結成したのが始まりだそうです。尾崎さんと共に頑張っておられる女性陣も大変バイタリティを持っておられ、こういう方がおられるからこそ事業が成功し、自殺者数が減っているということを現場で感じることが出来ました。

右松たかひろ
■住吉事務所(宮崎市北部10号線)/(写真および地図)
〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内1572番地6
TEL : 0985-39-9211 FAX : 0985-39-9213
□E-mail : info@migimatsu.jp (宮崎事務所本部連絡所および宮崎市北部10号線住吉事務所共用)
□Twitter :https://twitter.com/migimatsu5
- ボランティア各種団体活動 (216)
- 党務(自民党)活動 (100)
- 各種勉強会・講演会 (40)
- 宮崎の人モノ紹介 (12)
- 宮崎の祭り・行事・イベント (110)
- 家族・プライベート・ご挨拶 (91)
- 後援会活動 (276)
- YouTubeチャンネル (19)
- 右松政経塾 (4)
- 各地区後援会 (14)
- 後援会連合会壮年部 (1)
- 後援会連合会女性部 (11)
- 後援会連合会役員 (5)
- 後援会連合会青年部 (2)
- 県内全域(県北地域) (7)
- 県内全域(県南地域) (3)
- 県内全域(県央地域) (2)
- 県内全域(県西地区) (1)
- 県内全域(県西地域) (2)
- 資金管理団体志隆会 (18)
- 隆援会(企業後援会) (1)
- 時事問題 (62)
- 県議会・議員活動 (332)
- 選挙 (76)
- 「右松八策」 (12)
- 4期目県議選 (24)
- 現役大学生からの質問 (4)
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (11)
- 2025年11月 (16)
- 2025年10月 (11)
- 2025年9月 (8)
- 2025年8月 (4)
- 2025年5月 (11)
- 2025年4月 (9)
- 2025年3月 (11)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (13)
- 2024年12月 (20)
- 2024年11月 (20)
- 2024年10月 (20)
- 2024年9月 (20)
- 2024年8月 (20)
- 2024年7月 (20)
- 2024年6月 (20)
- 2024年5月 (20)
- 2024年4月 (20)
- 2024年3月 (22)
- 2024年2月 (20)
- 2024年1月 (20)
- 2023年12月 (20)
- 2023年11月 (20)
- 2023年10月 (20)
- 2023年9月 (20)
- 2023年8月 (20)
- 2023年7月 (9)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (20)
- 2023年3月 (19)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (3)
- 2022年8月 (8)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (3)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (3)
- 2019年5月 (5)
- 2019年4月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (2)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (5)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (6)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (3)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (3)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (3)
- 2017年2月 (3)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (2)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (1)
- 2016年7月 (3)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (3)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (2)
- 2015年10月 (5)
- 2015年9月 (6)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (7)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (8)
- 2015年3月 (6)
- 2015年2月 (10)
- 2015年1月 (2)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (2)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (10)
- 2014年8月 (10)
- 2014年7月 (2)
- 2014年6月 (4)
- 2014年5月 (10)
- 2014年4月 (10)
- 2014年3月 (10)
- 2014年2月 (10)
- 2014年1月 (10)
- 2013年12月 (10)
- 2013年11月 (12)
- 2013年10月 (10)
- 2013年9月 (10)
- 2013年8月 (12)
- 2013年7月 (17)
- 2013年6月 (12)
- 2013年5月 (6)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (6)
- 2013年2月 (10)
- 2013年1月 (8)
- 2012年12月 (6)
- 2012年11月 (17)
- 2012年10月 (16)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (10)
- 2012年7月 (7)
- 2012年6月 (8)
- 2012年5月 (13)
- 2012年4月 (15)
- 2012年3月 (8)
- 2012年2月 (12)
- 2012年1月 (10)
- 2011年12月 (8)
- 2011年11月 (14)
- 2011年10月 (14)
- 2011年9月 (14)
- 2011年8月 (18)
- 2011年7月 (17)
- 2011年6月 (15)
- 2011年5月 (21)
- 2011年4月 (16)
- 2011年3月 (29)
- 2011年2月 (4)