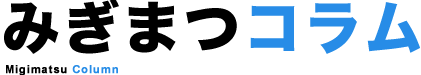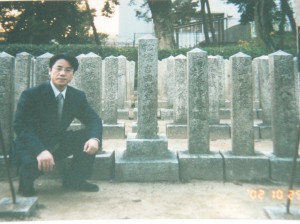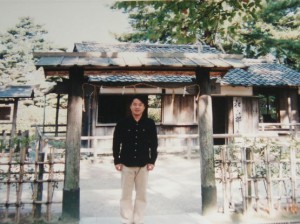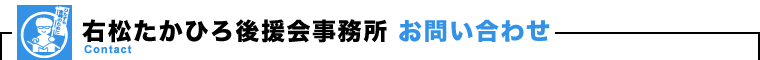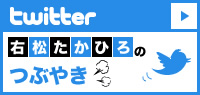ホーム > みぎまつコラム
みぎまつコラムでは、宮崎県や国が抱える様々な問題・課題、或いは時事を取り上げ、右松たかひろ の思いや考えていること、更には政策提言などを掲載しております。県央宮崎にお住まいの方はもちろんの こと、県内各地、さらには県外の方々にもお読み頂ければありがたく思います。ご一読下さいまして、ご感想やご意見などがございましたら忌憚なくお寄せ下さい。
ごあいさつ~不惑の歳、雌伏の時~
2008年06月08日
先日40歳になりました。40代とは、論語で言う「四十にして惑わず、五十にして天命を知る」になぞらえば、惑うことがなくなり、自身の天命を知るまでの10年間となります。今は、この雌伏(しふく)の時を辛抱し、志を見失わず、為すべき事を積み重ねていくことに専念する時と自らに言い聞かせております。
この半生を振り返ると、20代の半ばで仕事に大きな試練が訪れました。それを乗り越え、政治活動に入るまでの11年間やり通し結果を出すことが出来たのは、良き同僚・上司に巡り会えた幸運と、「信じる力」そして「執念」がそこにあったからではないかと思います。勿論、その二つの力も、毎日100軒から200軒もの飛び込み訪問をこなしてきた日常活動に対する自負が根底にあったわけですが、 この経験・体得が、今の私を形成していると感じています。
地元での政治活動に入ってからまもなく丸3年を迎えます。この間に一つの選挙を経て、様々な葛藤や忸怩(じくじ)たる思いを味わうも、皆さまのお陰で気持ちを切らさずにここまで戻って来ることが出来ました。もう、失うものはありませんし、あとは自らの志を信じて、這い上がっていくだけだと信じております。私の体に染み込んだ「志を信じる力」と「執念」を、来たるべき時に備えて培っておきたいと決意しておりますので、どうかこれからもご支援を賜りますよう宜しくお願いいたします。
右松たかひろ
自民党の党是:自主憲法の制定に向けて(2)~前文~
2008年05月29日
第1回は憲法を考えていく前提として、その成り立ち・成立の過程について触れ、国民が自らの手によって憲法を創る、自主憲法を定めることの意義を書かせて頂きました。 今回から、個別の内容に入っていきたいと思いますが、まず前文について考えたいと思います。前文は、日本という国がどういう国なのかが日本国民はもとより諸外国の人たちからも分かり、併せて、国家の理念、国の目指すところが何なのかということを明記することが肝要になってきます。
現行の日本国憲法の前文を読んでみますと、始めの段落に、人類普遍の原理として、主権在民の宣言と選挙で選ばれた国民の代表者が権力を行使し、その福利は国民が享受する、とあります。そして次の段落では、日本国民が恒久の平和を念願することと、全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認する、とあります。そして三段目に、いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないという普遍的な政治道徳を謳っています。
下に添付の憲法前文から、細かい内容で腑に落ちない点を順に申し上げると、1点目が下線①の部分です。過ちを政府の行為とはねつけるのではなく、国や先祖の責任を自らの責任と捉えることで、国への帰属意識(愛国心)や参政の意識も高まり、能動的に国家の存在価値を高めていこうと意識付けが出来るわけで、国家と国民を切り離す行為、政府と国民が一体であることを否定することは、引いては、自国の力を弱めることに他ならないと考えます。2点目が下線②の部分で、他国民の性善説に我が国の安全と生存を委ねるとは、主権国家としてはあまりにも危険で、かつ受動的過ぎると考えます。これでは自国への誇りや国際平和に向けて主体的に取り組もうとする力を培うことは難しいものと考えます。そして3点目の下線③の部分ですが、日本語の使い方もさることながら、理念が先行し、どこの国の憲法か分からない内容になっています。
しかし何と言いましても、残念ながら、この前文では大事なことが欠落していると言わなければなりません。その欠落しているものが、我が国の悠久の歴史であり、伝統や文化であり、国の矜持なのです。 また、日本語の使い方も、もう少し分かりやすく、親しみやすい文体に変えていく必要があると思います。なお、前文が国連憲章(国際連合憲章)に似通っているところに、国籍不明となってしまう所以があると考えます。
最後に、自主憲法を制定するにおいて、前文をつくる際に押さえておくべきポイントを下記に挙げたいと存じます。
一、我が国の伝統精神~「和を尊ぶ」「衆知を集める」「主体性を持つ。主座を保つ」
二、自然を畏れ、自然と共生をする文化
三、有史以来、天皇陛下が日本の元首であり、これからも我が国の発展と共に歩まれること
四、国際平和、諸国民の共存互恵の実現に資するを国家の目指すところに置く
五、国民の自由と権利を尊重するとともに国家の一員としての責任も有す
六、国と国民が共に、新しい国づくりへ進むことを期す
◆【自民党:今こそ自主憲法の制定を(自民党ホームページ「コラム」】~平成26年(2014年)10月に追記
右松たかひろ
公職選挙法改正の方向性について
2008年05月15日
公職選挙法の改正に向けての動きを注視しています。自民党の選挙制度調査会が選挙運動の規制緩和について主な8項目について合意され、今後は野党とも調整し、今国会中にも議員立法で改正案を提出することが3月11日に了承されました。 今国会の会期が残り1ヶ月弱に迫ってきている中で、未だ法案が提出されない現状に懸念を抱きつつも、「世界でも類を見ない内容」とも言われる我が国の公職選挙法において、時代にそぐわない内容や必要以上に規制がかけられた内容については、国政に携わる者の責務として、そして何よりも国民が政治との接点をより深め政治への関心を高めていく上でも、一刻も早く改めるべきであろうと考えます。合意内容について、当初の報告書案では明記をされていたものが反対論が相次ぎ盛り込まれなかったものがあります。具体的には、政党や団体の政治活動用ポスターの選挙前一定期間内(任期前6ヶ月以降に横行するの政党二連ポスター)掲示禁止や慶弔電報の禁止などです。やはり、政党人(公認者)や現職の優位性は保っておきたいとの思惑が無いとは言い切れない内容です。一致した項目で主なものは、屋内演説会場での映写の解禁や選挙カーの車種緩和や取り付ける文書の自由化、選挙ポスターの規格統一などです。しかし、もっと実態や時代に即した改正案、例えば、インターネット選挙の全面解禁や政党候補者と無所属候補者の選挙運動における様々な差別の撤廃や事前規制などについて踏み込んでいかなければ、有権者のための法改正とは言えないわけです。
投票率の低さや選挙への無関心が改善されない一つの要因に、公職選挙法を挙げている方が少なからずおられます。候補者について限られた情報や方法でしか入手が出来ない現行の公職選挙法では、有権者に正確で分かりやすい情報の提供を阻害しかねないとも限りません。良い候補者を選定するために欠かせない、国民の知る権利を十分に満たした選挙法へと改めていく必要があります。民主主義の根幹を成す選挙制度は、もっと国民や有権者に開かれたものでなくてはならないと考える次第です。
右松たかひろ
日本および日本人の国際社会での使命
2008年05月10日
20世紀が世界戦争の時代ならば、21世紀初頭は地域紛争・テロの時代と言えます。19世紀の植民地政策の時代を経て、20世紀は科学技術の飛躍的発展と共に大量殺戮を可能とする化学兵器も生み出され、国際社会を巻き込み二度の世界大戦というかつてない大規模戦争を経験することとなりました。ソビエト連邦の崩壊によって米ソ二大国の東西冷戦が終結したのが20世紀終わりの1991年で、その後は社会主義体制下におかれた旧東側地域を中心に民族・宗教間の対立が引き金となり地域紛争が多発していく中で、世界のパワーバランスはアメリカが唯一の超大国となり一国覇権主義へと大きく転換し、世界も驚愕した「アメリカ同時多発テロ(いわゆる9.11)」という、今後の国際社会を暗示する象徴的な事件によって21世紀が幕開けすることとなりました。その後は周知の通り、翌2002年1月にブッシュ大統領の一般教書演説での「悪の枢軸」発言に沿って、アメリカ主導の多国籍軍による武力行使が徹底的に行われました。兵器も今やIT革命によるハイテク兵器へと変貌し、戦争の形態も国家間よりもテロ組織や過激派集団との戦争行為が増えて来ています。
私は、このような国際状況下において、日本の果たす役割は決して小さいものではないと思っています。むしろ我が国は、東洋人としての民族の苦難を経験し克服もしてきた誇りがあり、且つ唯一の被爆国として戦争の凄惨さも知り得る立場から、「国際平和を導く」という大変重い使命があるものと認識しています。そこには、防衛力(武力)を放棄して国際平和を実現しようと試みる観念的平和主義に組する考えはなく、あくまでも日本の歴史や伝統・文化を基調とした国柄、経済力や軍事力などの国力、そして日本人の勤勉さや協調性、和を尊しとする国民性といった日本および日本人の総合力をバックボーンに、現実路線で戦略的に国際平和へ向けて主導していくことが肝要と考えている次第です。
日本および日本人の総合力を発揮していくには、我が国の潜勢力を掘り起こしていかなければなりません。そのためには、「普通の国」になることです。普通の国になってこそ初めて国際社会での発言力も出てくるものです。「普通の国」とは、自らの憲法を持ち、自らの国は自らで守るという国際社会においては当たり前の国家の姿にあります。国際平和へ導くという使命を実現する上でも、日本はもう一度生まれ変わらなければなりません。
右松たかひろ
吉田松陰の至誠と知行合一
2008年05月05日
 私の私淑する歴史上の人物で、まず真っ先に挙げたい人が、明治維新の胎動を起こした、不世出の指導者、吉田松陰です。吉田松陰という人物は、「至誠」と「知行合一」を抜きにして語ることはできません。 私は、現代日本の政治リーダーに、最も必要とする資質こそが、この至誠と知行合一だと思います。「至誠」とは、読んで字のごとく、極めて誠実なこと、真心(まごころ)・誠を尽くすことです。そこには、軽薄さや姑息な心は微塵も存在しません。そして、人を信じ、他人を活かすためには自己犠牲をもいとわない、高尚で純粋な心を松陰は持っていました。獄中で書いた遺書ともいうべき「留魂録」に、「私が死んだのち、もし同志の諸君の中に私の真心を憐れみ、志を受け継いでやろうという人がいるなら、それはまかれた種が絶えずに穀物が年々実っていくのと同じである」と書き記しています。天下国家のためには自らの死を持ってしてでも、同志に後世を託す、その至誠は人間として究極の美学であると深く感じ入ってしまいます。また、松陰を象徴するもう一つの言葉である「知行合一」は陽明学の真理でもあります。松陰は常々、門下生に「学者になってはいかぬ。人は実行が第一である。学んでも行動しなければ社会の役には立たず、学ばずに行動すれば社会に害をもたらす。」と言ったとされます。松陰のその類まれな行動力に、至誠が伴っていたからこそ、志ある者がどんどん感化されていったわけです。そしてその至誠は、祖国、先祖を愛し、救国済民のために、国柄を生かし正しい国のかたちをつくろうとする政治思想の裏付けがあったことは言うまでもありません。
私の私淑する歴史上の人物で、まず真っ先に挙げたい人が、明治維新の胎動を起こした、不世出の指導者、吉田松陰です。吉田松陰という人物は、「至誠」と「知行合一」を抜きにして語ることはできません。 私は、現代日本の政治リーダーに、最も必要とする資質こそが、この至誠と知行合一だと思います。「至誠」とは、読んで字のごとく、極めて誠実なこと、真心(まごころ)・誠を尽くすことです。そこには、軽薄さや姑息な心は微塵も存在しません。そして、人を信じ、他人を活かすためには自己犠牲をもいとわない、高尚で純粋な心を松陰は持っていました。獄中で書いた遺書ともいうべき「留魂録」に、「私が死んだのち、もし同志の諸君の中に私の真心を憐れみ、志を受け継いでやろうという人がいるなら、それはまかれた種が絶えずに穀物が年々実っていくのと同じである」と書き記しています。天下国家のためには自らの死を持ってしてでも、同志に後世を託す、その至誠は人間として究極の美学であると深く感じ入ってしまいます。また、松陰を象徴するもう一つの言葉である「知行合一」は陽明学の真理でもあります。松陰は常々、門下生に「学者になってはいかぬ。人は実行が第一である。学んでも行動しなければ社会の役には立たず、学ばずに行動すれば社会に害をもたらす。」と言ったとされます。松陰のその類まれな行動力に、至誠が伴っていたからこそ、志ある者がどんどん感化されていったわけです。そしてその至誠は、祖国、先祖を愛し、救国済民のために、国柄を生かし正しい国のかたちをつくろうとする政治思想の裏付けがあったことは言うまでもありません。
ちょうど今から5年半前、平成14年10月25日から26日にかけて1泊2日で山口県の下関や長府の功山寺、萩の城下町を、当時の琴線に触れるべく一人旅したことを思い出します。史跡巡りをしながら何ともいえない幸福感や気持ちの高ぶりを感じ、志を固めたのを覚えています。
リーダーというものは、「志の高さ」によって価値が決まるのであって、今の地位や過去の業績、年齢、ましてや貧富などによって価値が決まるものではないことを申し上げて、リーダー学での初稿の結びとさせて頂きます。
(下関市の櫻山神社招魂場/中央が松陰の霊標) (萩市の松下村塾跡)
右松たかひろ
自民党の党是:自主憲法の制定に向けて(1)~成り立ち~
2008年05月03日
憲法は言うまでもなく、国の最高法規になります。そして憲法とは、自国の歴史や伝統文化、国柄や国民性、価値観、アイデンティティというものが表現され、併せて主権国家としての体をなしたものでなければなりません。そのことは、どこの国の憲法にも、その前文において、自国の由来するところを明確にし、民族性が自己認識できることからも明らかであります。
我が国では、しばらく前までは、憲法論議をタブー視する風潮が見受けられもしましたが、近年では世論調査で6割以上の方々が改憲することに容認をされています。現行憲法が施行されてちょうど61年経過したわけですが、この間、同じく先の大戦で敗戦後に憲法を制定したドイツでは、時代の変化とともに50回以上もの改正が行われてきたにもかかわらず、我が国ではただの一度も改正されないばかりか、憲法論議自体もろくに行われてきませんでした。政治の本質的な存在意義が問われかねない中、昨年ようやく「日本国憲法の改正手続きに関する法律(国民投票法)」が可決され、再来年の平成22(2010)年5月18日施行されることとなりましたので、まさにこれから国民と共に認識を深めていき、政治家も自らの主義主張を訴えていく時が来たのだと思います。
国民的論議を促していく際、個別の条項を論じる前に、まずはその「成り立ち」をしっかりと共有していくことが大事であろうと思います。現行の日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布、翌22年5月3日に施行されたのですが、当時の日本はアメリカの占領下に置かれていました。日本が独立を果たしたのは、サンフランシスコ平和条約締結後の昭和27年4月28日であります。占領下で行われた日本国憲法の草案づくりにおいても、当初は松本烝治(じょうじ)国務大臣を中心に行われていましたが、その内容に連合国側が承知をせず、マッカーサー元帥が部下でGHQ民政局のケーディス陸軍大佐に作り直しを命じ、憲法学者が一人もない、24名のチームによって、僅か1週間で出来上がったのが真実であります。つまり日本国憲法は、原文が英語で、アメリカ人が作った憲法と言えるわけです。これでは、憲法の精神が、我が国の歴史や伝統、文化に即したものになろうはずもありません。冒頭申し上げましたように、国家の基本法である憲法はどこの国でも、国のアイデンティティを明確に謳っています。憲法とは、その国の国民が、自らの手によってつくられたものでなくてはならないのです。
今回は、憲法を論じていく上において大前提とも言える、「成り立ち」について申し述べさせて頂きました。
◆【自民党:今こそ自主憲法の制定を(自民党ホームページ「コラム」】~平成26年(2014年)10月に追記
右松たかひろ
大企業の法人課税について
2008年05月01日
国内企業において大企業が占める割合は僅か3%程度ながらも、雇用では全労働者の3割近くを担っています。また、法人税を収めている利益計上企業が全体で3割にも満たない中で、法人税収の寄与度を見ますと、資本金1億円以上の大企業で全体の65%も占めているのが現状です。そういった中、経済界を中心に、「日本の法人税率は諸外国に比べ高いのでもっと下げるべきであり、財政の健全化を図るための税制改革で最大のテーマは消費税の引き上げにある」との主張が聞かれますが、仮に、国税部分に当たる法人税を現在の30%から20%に引き下げた場合、税収が約4兆円も落ちることになります。現在の30%の水準に至るまでに、この20年間で税率が12%引き下げられており、法人税収面でも19年前の19兆円の規模から直近の平成18年度が13兆8千億円と28%も目減りしていることも併せ鑑みて、且つ、法人税の減収分を消費税の増税でまかなうということになれば、国民の理解が得られるとは思えないわけです。それでもあくまで、国際比較から法人税率の削減を主張するならば、欠損金の繰り延べを5年から7年に延長した税制改正を見直し、期間を短縮することで、欠損企業の割合を減らし、今まで営業収益を上げているにもかかわらず法人税を免れていたところを是正していく必要があると思います。大企業の中でも、欠損企業となって法人税を免れている企業が4割も存在をしていると言われます。少なくとも、資本金1億円以上の大企業などは売り上げに応じて法人税を納めるように改めていかない限りは、経済界が主張する法人税の引き下げについて、現在の財政状況から検討するのは難しいと考えます。(ちなみに、資本金1億円以上の企業で今まで法人税を納めなくて済んだ欠損企業が営業収益に見合った税を負担すれば、3兆6千億円も税収入が上がるという試算も出ています。)
尚、法人税の実効税率を国際比較で見てみると、日本が国税の法人税と地方税の事業税・住民税を足した実効税率が40.69%に対して、アメリカ(カリフォルニア州)40.75%、ドイツが今年から減税され29.83%、フランスが33.33%、イギリスが今月から減税され28%、中国が33%から本年度以降は一気に減税され25%、韓国が27.50%となっています。一見すると、我が国の法人税の実効税率は比較的高い水準にあると見がちですが、社会保険料率や控除制度、或いは消費税率など、他国の税制全般から考えると、単純に法人税率だけでは課税の重さは比較ができない側面があります。
右松たかひろ
皇室典範改正(女系天皇)の問題について
2008年04月24日
「皇室典範に関する有識者会議」が2004年12月27日に設置され、翌2005年11月24日に拙速にも女系天皇の容認および長子優先の報告書を出されました。女性天皇と女系天皇とは持つ意味が全く違うもので、決して混同してはならない概念であります。過去の歴史を紐解くと、女性天皇は推古天皇の始め8人おられましたが、母方が皇統を有し父方は皇族以外となる、いわゆる女系の天皇陛下は一人も存在されないどころか、父方が皇統でなくなるということは、血統が変わることを意味し、日本有史以来、父方が皇統を有する男系で皇位継承が行われてきた万世一系の伝統がそこで途絶え、全く新しい王朝が誕生することになるわけです。
また、長子を優先するという内容も理解に苦しみます。そもそも皇位継承では、皇室の方々のご意向がまず第一にあって然るべきでありますし、僅か1年足らず34時間の論議で、男系の男子が継承をすると定めた皇室典範第一条をひるがえしてまで、このような方針を示すとはあまりにも乱暴な話ではないかと思うのです。
平成18(2006)年9月6日に、秋篠宮紀子妃殿下に待望の悠仁親王様がご誕生されました。41年振りの男性皇族のご誕生で皇室典範の改正は一気にトーンダウンをしたわけですが、今後もまた同じような改正の話が繰り返されないためにも、敗戦後、GHQの指令で皇籍を離脱された旧宮家の8宮家の方々の皇籍復帰も前向きに検討されて良いのではないか思います。
国家の存在価値というものは、その国固有の歴史や伝統を形成してきた基(もとい)を護ってこそ高められるものと考えます。時代の変遷の中でも連綿と受け継がれ、取り巻く国際状況が激動していく中においても、先人の方々の叡智によって護り抜いてこられた基(もとい)が、万世一系の男系に連なるご皇室なのです。2000年に亘る日本史の重みというものをしっかりと噛み締め、たかだか数十年しか生きられないひとときにおいて、唯一無二の伝統を変えるという歴史への冒とくを犯してはならないと考える次第です。
右松たかひろ
宮崎の雇用(2)~低迷する有効求人倍率と給与水準~
2008年04月21日
宮崎県の山積する諸課題の中において私が特に重要視しているのは、厳しさを増す県内の経済情勢が如実に反映される指数として、改善の兆しが一向に見えない有効求人倍率と低い給与水準にあります。本県のここ1年間の有効求人倍率(パートを含む)の推移ですが、0.70から徐々に下降線を辿り、直近の平成20年2月は0.60となっています。同じ2月の全国平均0.97に遠く及ばず、全国順位もワースト7位となっています。
その地域での人口構造や産業構造の特色に強く左右されるのが雇用情勢であるとはいえ、これからますます地方分権化が進み、自己責任が問われる行政システムの下に自立した地方自治体を築いていかなければならないことを考えると、格差拡大を構造のせいにできない事情があるわけです。概して、有効求人倍率が良好な地域での産業構造は製造業の比率が高く、厳しい地域は第三次産業と政府依存型産業(建設、福祉など)の占める割合が高いという統計が出ています。お隣の大分県は全国平均に勝る有効求人倍率を誇っていますが、企業の大型誘致の成功や産業集積のバランスが取れていることで、「ものづくり立県」としての地位を築いています。有効求人倍率を上げるための特効薬を見出すのは難しいのですが、やはり現在取り組んでいる企業誘致に一層尽力していくことやベンチャービジネスなどの起業・創業の環境整備を図っていくこと、更には産学官の連携をより深めていき、地域固有の産業を集積していくことが求められると考えます。そしてそこには、地方主権の中で生き残っていくための大きな鍵ともいえる、自治体職員の地域再生に対する危機感と使命感に根ざした企画力や政策実行力が必須条件であることは言うまでもないことです。
有効求人倍率と同様に、給与水準も低いのが本県の実情です。厚労省の公表数字によると本県の所定内給与額は、男性が26万7600円(42.6歳、勤続12.4年)で全国ワースト4位、女性が18万2000円(40.5歳、勤続8.4年)でワースト2位となっています。これは、民間事業所の給与水準です。公務員天国と言われることは不本意なことで、民間が活性化されてこそ、地域再生に一筋の光明が差すものです。
右松たかひろ
地方分権のかたち(1)~自立する地域と国家へ~
2008年04月13日
「平成の大合併」によって基礎自治体としての枠組みが大きく変わりはしたものの、駆け込み合併の要因の一つである合併特例債のバラマキによって、逆に財政悪化につながった自治体や、いわゆる三位一体の改革と叫ばれる中で地方交付税が削減されたことで、財政難や住民負担の増大につながる自治体が発生しているという、様々な問題点が一方で露呈しています。税財源の移譲で、真の地方分権実現を見据えた改革には程遠いものと言わざるを得ません。そもそも、地方税を充実させるための自治体裁量権の拡大、つまり課税権の移譲が三位一体改革の趣旨であることに私は大きな疑問を抱いておりまして、本来は、国と地方の役割分担を明確にし、国家財政を地方へ移譲していくことで地方分権への道筋をつくっていくことが目指すかたちではないかと考えております。従って、上記一連の改革は、地方分権改革と言うよりも、むしろ一つの財政改革と言った方が適切であろうと思います。
さて、今から136年前に、明治新政府によって現行の国のかたちの基礎となる中央集権国家体制が築かれたわけですが、戦後改革を経て60年が過ぎた今、官僚統治機構の制度疲労が否応なく目に付いてきており、国益や国際競争力、更には地域活性化という観点からも、現在の統治システムが成長への大きな足かせとなっていることは明白であろうと思います。肥大化した国家システムから、決定プロセスの簡略化や無駄なコストの削減を図っていくことと、今後ますます激動が予測される国際社会への的確な対応力を培うには、国家の役割を絞っていき、内政における権限の多くを地方や地域に移譲していく「地方主権国家」という新たなパラダイムシフトを志向していくことが求められます。基礎自治体の主体として、道州制の導入もその一環として取り組んでいかなければならないと考えます。
防衛、外交、司法、教育の基本政策、マクロ経済、通貨通商、エネルギー政策、年金や医療など社会保障基盤のように、国の基本にかかわる統一的政策のみを国政が担い、中央行政のスリム化を徹底して行い、国際社会で真に自立することが、国家としての至上責務と存じます。そして基礎自治体においては、地域住民および地方自治体が主体的に物事を決定し、個性豊かな地域社会を形成していくと同時に、結果責任も負う行政システムを構築していくことが肝要になってまいります。
右松たかひろ
■住吉事務所(宮崎市北部10号線)/(写真および地図)
〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内1572番地6
TEL : 0985-39-9211 FAX : 0985-39-9213
□E-mail : info@migimatsu.jp (宮崎事務所本部連絡所および宮崎市北部10号線住吉事務所共用)
□Twitter :https://twitter.com/migimatsu5
- 年次別 (133)
- 2024(令和6)年度 (11)
- 2023(令和5)年度 (15)
- 2022(令和4)年度 (2)
- 2021(令和3)年度 (1)
- 2020(令和2)年度 (3)
- 2019(令和元)年度 (1)
- 2019(31)年度 (1)
- 2018(平成30)年度 (3)
- 2017(平成29)年度 (5)
- 2016(平成28)年度 (2)
- 2015(平成27)年度 (2)
- 2014(平成26)年度 (11)
- 2013(平成25)年度 (9)
- 2012(平成24)年度 (9)
- 2011(平成23)年度 (4)
- 2010(平成22)年度 (4)
- 2009(平成21)年度 (12)
- 2008(平成20)年度 (38)
- カテゴリ別 (133)